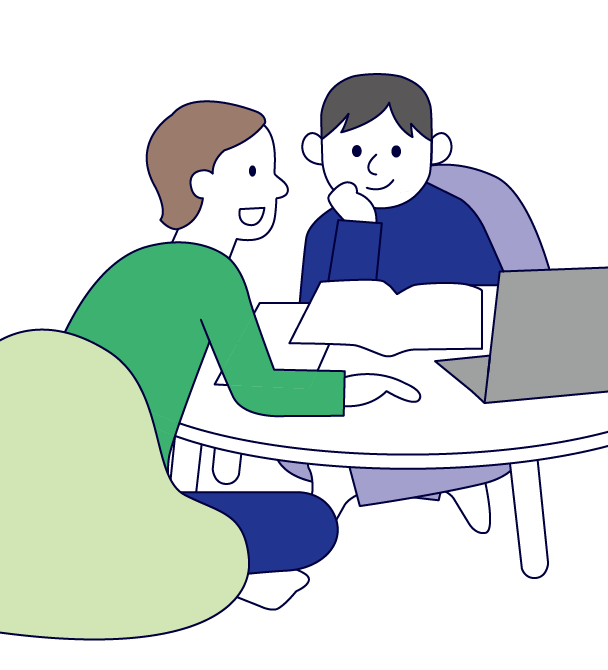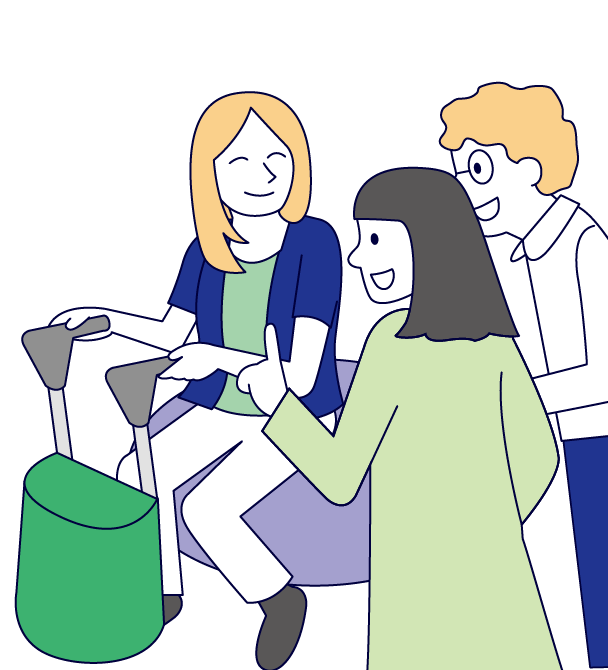About
人科 DE&Iプロジェクト

DE&I(Diversity, Equity and Inclusion)とは?
DE&Iは、Diversity(多様性), Equity(公正性) & Inclusion(社会的包摂)の頭文字3字をとった略語です。
ダイバーシティ(多様性)とは、人種、性別、宗教、価値観などが違う人たちが共存する状態をさします。ダイバーシティは、もとは人種や性別による差別をなくすことに重点が置かれていました。しかし今では、ライフスタイルや価値観、性的指向など、外部からは見えにくい、深層的、内面的な要素も含んだうえで、差別をなくし、共生を示す概念となっています。
エクイティ(公正性)は、違いや不利な状況を考慮して、必要な支援を行うことができれば、すべての人が平等な結果を享受できるという考え方です。
インクルージョン(包摂性)は、一人ひとりが組織やコミュニティの一員として尊重され、排除されることのない環境をつくるという考え方です。
<ロゴについて>
大阪大学がある北摂地域の障がい者団体のメンバーの方が描いたアートでつくりました。「DEI」の文字を囲む複数の輪は、ゆるやかに重なりあっています。一人ひとりの違いや特性を認めあい、誰一人取り残さない社会を目指したいという思いを込めています。

大阪大学が目指す
「多様な人材が輝く
グローバル戦略とDE&Iの深化」
大阪大学では、「大阪大学ダイバーシティー&インクルージョンセンター」(D&Iセンター)を核として、SOGI(性的指向・性自認)、障がいの有無、国籍、民族、文化的背景、年齢などの違いにかかわらず全ての学生・教職員が尊重される環境の整備に取り組んでいます。
また合理的配慮を必要とする学生に対する支援では「大阪大学キャンパスライフ健康支援・相談センター」(略称:HaCC)が大きな役割を果たし、さらに大学本部では障がいのある方の雇用機会を創る取り組みが進められています。
「多様な人材が輝くグローバル戦略とDiversity & Inclusionの深化」は、大阪大学の中長期的な経営ビジョン「OU(Osaka University)マスタープラン2027」の基本方針の1つであり、大阪大学は多様性を尊重し、その多様性を真に活かすことのできるインクルーシブな学内環境の創出を目指しています。
***
人間科学研究科は、DE&Iの考え方を基盤とした「社学共創によるWellbeingで
Inclusiveなキャンパスづくりの全学展開に向けた試行」(通称:「DE&Iプロジェクト」)を提案し、「令和6(2024)―8(2026)年度人科OUマスタープラン実現加速事業」(活性化A)の採択を受け、活動を始めました。DE&Iにみるさまざまな課題のなかでも、特に障がいのある人たち、しんどさを抱える学生や教職員を支え、すべての構成員が持つ力を十分に活かすことができるキャンパスづくりに挑戦しています。
大阪大学ダイバーシティ&
インクルージョンセンター
大阪大学 キャンパスライフ
健康支援・相談センター(HaCC)

人科が取り組む
「DE&I実装キャンパス」―ディスアビリティを理解し、
インクルーシブなキャンパスを
●世界に遅れをとる日本の障がい者支援
障がいのある人もない人も支えあいながら、生き生きと暮らせる社会を目指す「ノーマライゼーション」の理念に基づき、世界各国で障がいのある人たちの支援が進められてきました。日本でも、法律や制度の整備が進められていますが、障がいのある人たちにとって「ノーマル」な地域生活が実現できているとはいえません。国連からは日本に対して、障がい者が自立した地域生活を送る権利が保障されていないとして、是正勧告が出されています。
●社会的包摂の考え方の一つとして ―誰でも支援が必要な「とき」がある―
社会的包摂とは、孤独や孤立が生まれないように、障がいや疾病の有無にかかわらず、一人ひとりを社会の構成員として包摂し支え合うという考え方です。社会的包摂の対象は、社会的に弱い立場にある人と思いがちですが、支援が必要な「ひと」は一様ではなく、誰でも孤独になりうるし、支援が必要な「とき」があるのです。そう考えると、ディスアビリティは決して他人ごとではありません。
人間科学研究科では、「大阪大学ダイバーシティ&インクルージョンセンター」(D&Iセンター)と「大阪大学キャンパスライフ健康支援・相談センター」(略称:HaCC)と連携し、学生・教職員の誰もがそれぞれの力を発揮できるキャンパスづくりに向けて、研究と教育の面からDE&Iの普及と定着を目指しています。人科の研究と教育の特技を活かして、3つの事業「人科版レジリエンス・サポート・ルームの創設」「DE&Iカフェ」「大阪大学大学院人文社会科学系オナー大学院プログラム『DE&Iデザイン』ユニット」に取り組んでいます。
DE&Iレジリエントキャンパスの
創設に向けて.pdf

大阪大学大学院人間科学研究科
研究科長西森 年寿
人間科学研究科の
研究と経験を活かす
人間科学部は1972年に誕生しました。以来、様々な社会課題に向かい合いながら、行動学、社会学、哲学、人類学、教育学などを中心に学際的な立場から、総合的な人間理解を目指してきました。
本プロジェクトは、次の 3 つの計画を実行し、その成果を全学に展開し、OU マスタープラン「多様な人材が輝くグローバル戦略と Diversity&Inclusion の深化」を目指します。
<計画 1>
キャンパスライフ健康支援・相談センター(HaCC)と協力し、工学研究科レジリエンス・サポート&トレーニングセンター(REST)の経験に学び、部局レベルで多様な相談に対応できる相談室を開設し、学生と教職員の包括的支援として、小規模な部局でも相談機能を高めるモデルに挑戦します。
<計画2>
障がいや多様性を理解する場として「DE&I カフェ」を開設します。大阪大学における障がい者雇用 の多様化と促進に貢献します。
<計画3>
本学ダイバーシティ&インクルージョンセンターと協働し、海外の研究者とともに 「DE&Iスタディー ズ」の研究領域を開発し、それを大学院教育の場で活かします。
現代の日本社会でDE&Iをどう実現・深化していくのか。この課題の解決には、まさに総合的な人間理解が求められると考えます。本研究科が積み上げてきた研究力と実践力で、本プロジェクトに取り組みます。

大阪大学大学院人間科学研究科
研究科長西森 年寿
HP内での「障がい」の表記について
このHPでは多くの自治体で採用されている表記方法を採用し、
人を表す場合は「障がい」、法令・制度を表す場合は「障害」と表記します。
DE&Iプロジェクト
-
人科版レジリエンス・
サポート・ルームキャンパスライフで発生する様々な事柄について、気軽に相談できる場所として、部局でのレジリエンス・サポート・ルームの開設を試行します。大阪大学キャンパスライフ健康支援・相談センター(HaCC)と連携し、小さな部局でも、学生・教職員問わず誰もが幅広いサポートが受けられる組織づくりを行います。
詳しくはこちら
-
レジリエンスを
向上させるプログラム学業、研究、仕事でそれぞれの力が発揮できるよう、一人ひとりのレジリエンスを高めるためのプログラムを実施します。「普段着で参加できるヨガクラス」「マインドフルネス・プログラム」「手話カフェ」を試行しています。
詳しくはこちら
-
大阪大学大学院人文社会科学系
オナー大学院プログラム「DE&Iデザイン」ユニット海外の大学とも連携しながら、博士後期課程院生を対象に、大阪大学で行われる多くの研究の基盤となりうるDE&Iデザインを学びます。大阪大学のDE&I研究を国際展開につなげます。
詳しくはこちら
連携
学内の関連機関と連携し、
DE&I実装キャンパスの実現を目指します
お問い合わせ
| 連絡先 | 大阪大学大学院人間科学研究科 「人科DE&Iプロジェクト」 (2024-2026年度OUマスタープラン実現加速事業) |
|---|---|
| 住所 | 〒565-0871 大阪府吹田市山田丘1−2 人間科学研究科棟 本館1F 「DE&Iプロジェクト」事務室 |
| hus-dei@office.osaka-u.ac.jp |